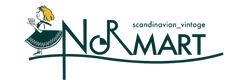2025.11.5
TAPIO WIRKKALA-THE SCULPTOR OF ULTIMA THULEタピオ・ヴィルカラ ー 世界の果て
2025年4月に東京で始まった「タピオ・ヴィルカラ展」。その後、8月には兵庫、そして10月25日より岐阜県現代陶芸美術館へと巡回してきました。
ヴィルカラは北欧フィンランドを代表するデザイナーで、1946年にイッタラ社のデザインコンペで優勝して以来、約40年間にわたり第一線で活躍しました。
イッタラの<ティーマ>シリーズを手掛けたしたカイ・フランク、そして同社の旧ロゴである<i>マークをデザインしたティモ・サルパネヴァと並びフィンランドデザインの三巨匠として知られています。
今回の回顧展は日本初の開催で、フィンランドのエスポー美術館に所蔵されている約300点のコレクションを中心に、写真やドローイングなどを通して、デザイナーでもあり彫刻家でもあったヴィルカラの多面的な魅力に迫る内容となっています。
僕は10月25日初日に、さっそく岐阜県現代陶芸美術館を訪れました。
この美術館にはこれまでも北欧関連の展覧会がたびたび巡回していて、北欧デザインの流れを地域に伝える貴重な場所だと感じています。
そして2026年4月頃には、僕のお店「ノルマート」の店舗ギャラリーも同じ多治見市でオープンを予定しています。
この地に北欧の企画展がやってくることを、地元民としてとても誇らしく思います。
ここからは展覧会を訪れて感じたことを、美濃焼の産地としての多治見という視点も交えながら、お話していきたいと思います。

TAJIMI AND SCANDINAVIA多治見と北欧
岐阜県現代陶芸美術館は岐阜県多治見市にあり、その名の通り「現代の陶芸」をテーマに日本と世界各国の陶芸作品やそれにまつわる資料などを収集している施設です。
多治見市のある東濃地方は「美濃焼」の伝統産業の産地としてしられ、世界でも有数な陶磁器産地となっています。
私も子供の頃から美濃焼に慣れ親しみ、日用品として当たり前のように使っていました。
美濃焼という伝統工芸を誇る場所だからこそ、美濃焼を含めた「工芸」を伝える意義があるように感じます。
過去の北欧展
岐阜県現代陶芸美術館には、これまでにも北欧の企画展はいくつか巡回してきました。それは美濃焼という伝統工芸のある地ということが一番の理由だと思います。
僕が過去に訪れた北欧の展覧会は、2021年6月に開催されたルート・ブリュック展、2023年12月のフィンランド・グラスアート展、2024年6月からのリサ・ラーソン展、そして今回のタピオ・ヴィルカラ展です。
普段はなかなか見ることのできない北欧のアートピースや貴重な資料などが地元で見れることは本当に嬉しいですし、とても誇らしいことです。
特に今回の企画展、タピオ・ヴィルカラの妻でもありフィンランド・アラビア社のアート部門で活躍したルート・ブリュックの展覧会は強く印象に残っています。
彼女が制作した陶板を中心とした作品は、ヴィンテージ市場でもほとんど見かけない貴重なアイテムばかり。いつか彼女のヴィンテージ作品にも出会えたらいいなと思っています。
美濃焼の伝統工芸を誇り、北欧の貴重な展覧会が巡回してくる多治見で、これからオープンするノルマートの存在意義を改めて考えていきたいと思います。

VISITING THE WIRKKALA EXHIBITIONヴィルカラ展を訪れて
岐阜県現代陶芸美術館はセラミックパーク美濃という施設の中にあります。
美術館へと続く長い回廊がとても美しく、両側には豊かな自然が広がっています。天井には陶磁器のかけらが埋め込まれており、この地が陶磁器の産地であることを改めて感じさせてくれます。
この先にヴィルカラがデザインしたガラスや陶磁器が並んでいると思うと、日本とフィンランドがどこかで繋がっているような、少し不思議な感覚になります。
ヴィルカラの代表作でもある<ウルティマツーレ>は、ラテン語で「世界の最果て」という意味を持ちます。彼が愛したフィンランド最北の地、ラップランドの幻想的な自然と静寂からインスピレーションを得たと言われています。
ヴィルカラはウルティマツーレをはじめ数々の名作ガラス作品を生み出しましたが、ガラスだけでなく陶磁器、グラフィック、家具など多様な素材にアプローチしたことでも知られています。
今回の展覧会では、ガラス以外の作品も多く展示されていました。ヴィンテージ市場ではガラス作品を見かけることはありますが、それ以外の作品を一度に見る機会は少なく、じっくりと堪能したいと思いました。
自然との共存が生むデザイン
まず、入口で出会ったプライウッド作品には圧倒されました。
流れるような木目の美しさと、複雑に表現された曲線。その造形にはしばらく目を奪われ、時間を忘れて眺めていたとほどです。
ガラス作品の中では、アンズタケをモチーフにした〈カンタレッリ〉も印象的でした。
フィンランドではきのこが身近な存在であり、自然を愛する文化がそのまま形となった作品だと感じます。
スポットライトに照らされたカンタレッリは、美しい陰影をまとい、静かに輝いていました。
また、ヴィルカラがデザインしたフィンランド紙幣や、アラビア製陶所のポスターなども展示されていました。これらは当時の時代背景を感じさせる貴重な資料です。
実は私もそのアラビアのポスターの復刻版を持っており、ノルマートの店舗ギャラリーと併設する自宅玄関の、いちばん目立つ壁に飾る予定です。
そして展示の後半には、ウルティマツーレの作品群が並びます。氷を思わせる造形は幻想的で、まるでラップランドの静寂そのものを表現しているようでした。
フィンランド国内での仕事にとどまらず、イタリアのヴェニーニによるガラスアートや、ドイツ・ローゼンタールの陶磁器など、国境を越えた活動の広がりも知ることができました。
北欧は厳しい寒さと短い日照時間の中で育まれた文化圏です。それでも人々は自然を愛し、寄り添うように暮らしてきました。その姿勢が、ヴィルカラのデザインにも深く息づいているのだと思います。
ヴィルカラ、そして妻ルート・ブリュック。二人のデザインの根底にある「自然との共存」という思想を感じ取ることができた、貴重な展覧会でした。

MEMORIES OF FINLANDフィンランドの思い出
2019年10月、初めてフィンランドを訪れました。
上空から見下ろした大地は湖と森に覆われ、日本とは異なる自然のスケールを感じたことを覚えています。
到着したのはヘルシンキ。なかでも印象に残っているのは、エスプラナーディ通りの公園で過ごした時間です。
通りにはマリメッコ、イッタラ、アルテックなど北欧を代表するブランドのショップが並び、ヘルシンキ最大のショッピングストリートと呼ばれています。
一方で緑と花が美しい公園が点在し、買い物の合間に市民や旅行者が思い思いにくつろいでいました。
天気のよい日で、ベンチに座って近くのスーパーで買ったブルーベリーを頬ばり、木漏れ日と風を感じながら、少し“フィンランド流”の過ごし方ができた気がします。
自然に向き合う時間は心を静めてくれる――その大切さをあらためて実感しました。
イッタラとアラビアへ
ヘルシンキを訪れた理由のひとつが、あの煙突で知られるアラビア・ファクトリーです。写真や資料で幾度も見てきた場所。
トラムを降りて少し歩くと、壁面の縦書き「ARABIA」と高く伸びる煙突が視界に現れ、胸が高鳴りました。
館内にはアラビアとイッタラのショップ、アウトレットがあり、ヴィンテージが驚くほど手頃な価格で並びます。パラティッシ柄のエレベーターを上がると、両ブランドの歴代プロダクトがずらり。
タピオ・ヴィルカラの作品もショーケースに展示され、なかでも「カンタレッリ」は何度見ても息をのむ美しさ。ガラス壁面には妻ルート・ブリュックの陶板も飾られていました。
これほどの名作群を一度に見られる場所は、他にないのでは――そう思わせる充実ぶりでした。

多治見で北欧の雰囲気を
ここまでタピオ・ヴィルカラ展と多治見市の特徴、フィンランドでの思い出についてお話してきました。
思い出せば27歳くらいのとき、多治見市のとあるコンテストで「多治見を北欧の街にする」というプランで応募したことがあります。当時はまだ北欧を訪れる前で、ノルマートもオープンしていない時期。僕自身、北欧についてまだまだ知識不足でした。
それから数年たった今、一度だけですがフィンランドにも渡り、北欧のヴィンテージ品に日々触れる中で、感じたことや気づいたことがたくさんあります。
そして来年春にノルマートの店舗ギャラリーがオープン予定。どんな風に北欧ヴィンテージを表現して、地域と関わっていくかを考えることがとても楽しいのです。
地域に貢献できるような立派で大きなお店ではないですが、美しいものを暮らしに取り入れることで幸せな暮らしになるということを、また新しい形で発信していきたいと思っています。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。