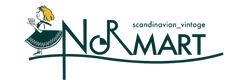2025.9.2
How to Enjoy Erik HöglundErik Höglundの楽しみ方
2025年からノルマートでも本格的に取り扱いを始めたErik Höglund(エリック・ホグラン)のアイテムたち。
最初は小さなガラスのアッシュトレイからスタートし、今ではベースやキャンドルスタンド、アートピースなど、少しずつ取り扱う種類も増えてきました。
これまではスウェーデンへの買い付けルートが少なく、ホグランの作品は珍しいものや高価なアイテムも多いので買い付けるタイミングが限られていました。
ホグランの作品はアート性があること、プリミティブの要素が含まれていることがヴィンテージ品として強い魅力を感じていました。
安定して買い付けができるルートが見つかり、皆さんにもホグランの作品の素晴らしさをお伝えできることが何より楽しみです。
買い付けを重ねる中で気づいたのは、「同じデザインでも全く違う表情を見せる」という点です。
もちろんヴィンテージアイテムには個体差がつきものですが、ホグランの作品はその枠を超え、同じアイテムでもまるで別の作品のように感じられるのです。
その違いこそが魅力で、どれだけ眺めていても飽きることがありません。
ホグランのアイテムをじっと眺めること
私自身も買い付けた後、ただひたすら眺める時間があります。
スウェーデンの当時の雰囲気や時代背景を想像しながら眺めるときもあれば、何も考えずにぼんやりと見つめているときもあります。
気づけば、その対象は圧倒的にホグランの作品が多いのです。
そんなふうに「ただ眺める」という楽しみ方こそ、ホグランのアイテムならでは。
ちょっと変わった楽しみ方かもしれませんが、同じように共感していただける方がいたら嬉しく思います。

Admiring bubblesホグランならではの気泡を愛でる
なんといってもホグランの作品の特徴は「気泡」 です。
ランダムに入り込んだ大小の気泡は、単なる製造過程の偶然ではなく、彼のデザインそのものを象徴する要素。最大の魅力と言っても過言ではありません。
たとえば写真のグレーのベースにも、無数の気泡が散りばめられています。その入り方が特に美しく、私のお気に入りのひとつです。まるで窓ガラスに付いた雨の水滴のようで、どこか神秘的な雰囲気さえ漂います。
気泡をじっくり眺めていると、「ここの気泡は丸くて綺麗だな」「この大きな気泡を小さな気泡が囲んでいるのが面白いな」と、自分の“好みの気泡”が見えてきます。
正円に近いものもあれば、楕円や歪な形もあり、同じものはひとつとして存在しません。
その様子は、空に浮かぶ雲を眺めているときの感覚に似ているかもしれません。
それは雲の形がアイスクリームのように見えたり、クジラの姿を思わせたり。そんなふうに観察しているうちに、自然と愛情が芽生えてきます。
きっとモノに愛着を持つというのは、まずは「じっくりと観察すること」から始まるのでしょう。
そしてその中に、自分だけの好みを見つけること。ホグランの作品は、まさにその体験を与えてくれる存在だと思うのです。
自然光に当ててみる
ガラスが最も魅力的に輝くのは、やはり自然光に照らされたときではないでしょうか。
陶磁器にも光の変化はありますが、ガラスは一層その表情が豊かで、光を受けた瞬間に命を宿したかのようにきらめきます。
その輝きは天候や季節によって異なり、同じ日でも太陽の位置や光の差し込み方でまったく違った姿を見せてくれます。
特に気泡の入ったガラスは、光を受ける角度によって陰影が移ろい、時に幻想的な表情を生み出します。
ほんの少し置き方を変えるだけで新しい表情が現れるのも、ガラスならではの楽しさです。
北欧では緯度の関係から太陽光を感じられる時間が限られていますが、日本では一日の中で刻々と変化する光の表情をより豊かに味わえるのかもしれません。
窓辺にガラスを置き、朝から夕方まで移りゆく光を眺めてみる──そんな一日を過ごすのも素敵ですね。

Compare the same items同じアイテムを比べる
ホグランの作品については、冒頭でも触れたように個体差の大きさが魅力のひとつです。しかし一方で、「同じ品番のアイテム」も存在します。
底部に品番やサイズがカットサインとして刻まれていることがあり、その番号が一致していれば、基本的には同一商品として扱われます。
この点は、当店でよく扱うRoyal CopenhagenやJens H. Quistgaardの陶磁器とも共通しています。
同じ品番があっても、釉薬の表情やサイズ感などに微妙な違いが生まれるのです。
ただし、ホグランの作品は特にその「個体差の幅」が大きく、同じ番号であっても並べてみるとまるで別の作品のように見えることすらあります。
同じ、でも異なる
上部の写真に写っているブルーの脚付きベースは、どちらも同じデザインですが、それぞれ異なる個体です。
写真では少し分かりにくいかもしれませんが、左のベースにはホグランらしい気泡が全体に入り、右の個体にはほとんど気泡が見られません。
どちらが良い、悪いということではなく、気泡そのものがデザインの一部となっているのです。さらに、ガラスの膨らみやサイズ、厚み、色合いなども一つひとつ異なります。
現代の工業製品は精巧で均一な品質を誇りますが、ヴィンテージアイテムには「完璧ではないところ」にこそ魅力があります。
同じデザインであっても、並べて観察することで違いが見つかります。
そしてその違いが「大切にしたい」という気持ちにつながり、やがて愛着へと育っていくのだと感じます。

Just decorate it.ホグランのアートをとにかく飾る
北欧ヴィンテージの中でも、ホグランの作品には「食器」が意外と少ないのをご存じでしょうか。
食器なら、日常の中でどう使うかをイメージしやすく、サイズ感もある程度決まっています。
一方でホグランのアイテムは、ベースやアートピースといった“飾ること”が前提のものがほとんどです。
だからこそ「どう飾ろう?」「どこに置こう?」と迷ってしまう方も多いかもしれません。
でも私は、もっと気軽に自由に飾ってほしいと思います。
自分が「いい」と感じた場所に置くだけで、その瞬間から空間は特別に見えるからです。
飾ってみて違和感を覚えたら、また移動すればいいだけ。ホグランの作品は気泡や鮮やかなカラーリングが特徴的なので、ひとつ置くだけでインテリアの主役になってくれます。
もしひとつだけ飾る場所をおすすめするなら、自然光の差し込む窓辺。時間や季節によって変わる光が作品を照らし、思いがけない表情を見せてくれるはずです。
飾ることの楽しさ
北欧の暮らしを訪ねると、壁や棚にアートやポスター、陶器のプレートなどを飾っている光景をよく目にします。
地震がほとんどないという背景もありますが、何より「飾ること」を自然に楽しんでいるのです。
それに比べて、日本の住宅やモデルルームは飾り気が少なく、どこか物足りなさを感じます。ミニマリズムが流行しているのかもしれませんが、インテリアの中で“視線を集める場所=フォーカルポイント”をつくることは、とても大切だと思います。
シェルフやサイドボード、テーブルの上に少し高さのあるものを置くだけで、空間に奥行きや立体感が生まれます。小さなお子さんがいても、ある程度の高さを意識すれば安心です。
先にお話ししたことと逆になりますが、「どう飾ろう?」と考える時間もまた、至福のひとときだと思うのです。

ここまでホグランのアイテムの楽しみ方についてお話してきました。彼の作品はユニークで個性溢れるものが多いです。
インテリアは参考事例や様々な媒体で紹介されているものをつい真似したくなりますが、その人のテイスト、個性を出すことが最も重要だと思っています。
ホグランのアイテムは個性を簡単にインテリアに取り入れることができるのでオススメです。
私が「個性」で買い付けたヴィンテージアイテムが誰かのインテリアの「個性」となることを願っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!